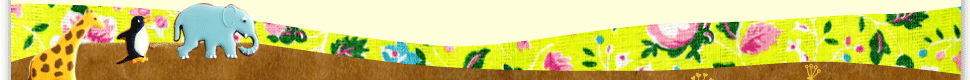7:00
8:30
10:00
11:30
11:50
12:30
13:00
15:00
15:45
16:00
16:15
17:15
17:45
18:00
20:00 |
登園(健康観察)
・挨拶をする
・延長の部屋で遊ぶ
クラスに移動
・視診をする。
持ち物整理
あそび
片付
手洗い、うがい
あそび
各種教室
「英語教室」
「手話教室」
「サッカー教室」
片付け
排泄
手洗い
食事準備
食事
片付け
歯磨き
休息
活動
(午睡 7月上旬〜9月中旬)
・ 室内あそび
・ 戸外あそび
「書道教室」
片付け
排泄
おやつ
降園準備
放送当番
降園・挨拶
延長保育
(延長の部屋に移動)
・ 戸外あそび
・ 室内あそび
片付け
軽食
あそび
降園 |
- 施設内外、遊具等安全点検をする。
- 興味や発達に応じて遊べるように環境を整えておく。
- 一人一人笑顔で挨拶をし、安心できるよう丁寧にできるように受け入れる。
- 必要に応じて保護者より連絡を受ける。
- 所持品の始末が速やかにできるように見守ったり、助言したりする。
- 気温などに合わせて衣服の調節を促す。
- 子どもの興味や要求に応じた環境を整え、したい遊びがスムーズにできるようにする。
- すべての子どもの遊びに目が届くようにする。
- 片付けやすいように環境を整え、保育士も一緒に片づけをする。
- 汗の始末、手洗い、うがい、をするように促し健康管理に努める
- 出席人数の確認をする。
- 個人差に十分留意をしながら個々の子どもの欲求に適切に応じ、保育士と子どもの信頼関係を深め、友だちと関わる中で個人や社会生活に必要な習慣や態度が身につくよう配慮する。
- 戸外では十分に身体を動かしたり、さまざまな遊具や用具を使った運動や遊びが楽しめるようにする。
- 友だちとの遊びを通して自分を主張しようとする態度や友だちの立場を認めようとする気持ちが育つように配慮する。
- 動植物と触れ合い、飼育栽培する中で、生命に関心を持ち自分たちの生活との関わりに目を向け、感謝したりいたわりの気持ちが育つように配慮する。
- 排泄・手洗い・うがい等が安全で清潔に行えるようにする。
- 当番にお茶や牛乳などを配るように声をかけ、当番活動の責任感を促し励ましていく。
- 友だちと一緒に楽しんで食事ができるよう配慮しながら偏食をなくすよう指導する。
- 食器は自分で片付けるよう言葉がけをし見守る。
- 食後の歯みがきが習慣として身につくように一緒に磨く。
- 午前中の遊びや活動、子どもの心身の状態などにより、環境設定を考慮する。
- 遊びを見守りながら保育士も一緒に遊びに入っていく。
- 子ども達と一緒に、保育士も思いきり体を動かし、開放感を味わうことができるようにすると共に、危険がないよう見守る。
- 片付けを進んで行えるよう声をかけ、保育士も一緒に片付ける
- 排泄や手洗いをするように促す。
- 楽しい雰囲気の中で食べられるようにする。
- 健康、持ち物、服装などの状態を確認する。
- 帰宅後の遊び、交通安全について注意をする。
- 明日に期待が持てるようにする。
- 年長児の放送当番を聞きながら交通安全に気をつけて行動できるように促す。
- 一人ひとりの親を確認し、必要事項を連絡し、挨拶をして帰す。
- 迎えがあるまで安全にゆったり遊べるようにする。
- 友達が帰る姿を見て寂しがる子どももいるので、一人一人が安定できるように接していく。
- 保育士の交代のため、人数確認をして引き継ぎをしっかり行う
- 長時間保育児に対して保育士や友達と安定した関係の中で楽しんで遊ぶように配慮する。また、異年齢児とも愛情を持って遊ぶよう援助する。
- 子どもと一緒に遊びながら安全面に配慮していく。
- 延長児の人数を確認をする。
- 楽しい雰囲気の中で間食が摂れるようにしていく。
- 紙芝居や絵本を読みゆったりとした雰囲気をつくる。
- 人数や安全を確認しながら静かな遊びを誘っていく。
- 暗くなり寂しがる子どももいるので、優しく声をかけながら一緒に遊んでいく。
- 迎えの人を確認し、伝達漏れのないようにする。
- 笑顔で見送り明日も元気に登園できるように声をかける。
|